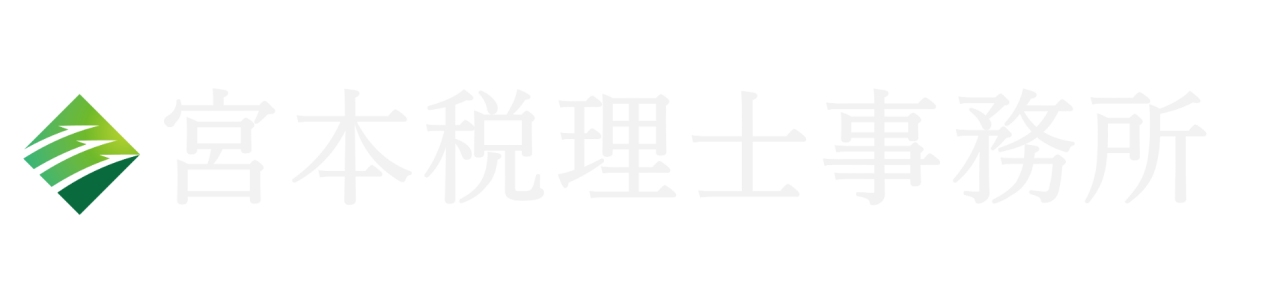相続時精算課税制度を利用するメリット・デメリット
2025/03/18
相続時精算課税制度は、世代間の資産移転を促進するために設けられた税制上の特例措置です。本来は暦年課税に従い毎年贈与税の処理を行うのですが、早期の資産移転がしやすいように課税のタイミングなどが工夫されています。
当記事ではこの制度について言及し、贈与者や受贈者、将来の被相続人や相続人にとってどのようなメリットがあるのか、逆にどのようなデメリットがあるのかを解説しています。
制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子どもや孫など)への贈与にのみ適用が認められる制度です。
暦年課税が原則であり、1人の受贈者が基礎控除額にあたる年間110万円以上の贈与をうけると贈与税の負担が発生します。しかし相続時精算課税であれば制度採用後、毎年110万円の基礎控除に加え累計2,500万円までの特別控除が適用可能となり、贈与時における税負担を大きく軽減することができます。
その分の課税は相続時へと先送りになるため、相続時精算課税の選択が直接的な節税効果につながるとは限りません。ただ、大学進学資金や起業資金の早期移転を図る場合などには有効な制度といえるでしょう。
また、基礎控除と特別控除を差し引いた残額については贈与税が課税されますが、このときの税率も通常とは異なり、一律20%の税率が適用されるという特色も持ちます。
相続時精算課税を選択するメリット
相続時精算課税を選択することには次のメリットがあります。
・2,500万円の特別控除と基礎控除が併用できる
・贈与時点の価格で相続税を計算できる
・収益物件による相続財産の増加が抑制できる
この3点に焦点を当てて同制度のメリットを紹介します。
2,500万円の特別控除と基礎控除が併用できる
近年、法改正を経て、相続時精算課税を選択しても基礎控除が使えるようになりました。
従来は2,500万円の特別控除のみが適用可能でしたが、2024年からはこれに加えて暦年贈与同様に年間110万円の基礎控除が適用できるようになっています。
たとえば年間500万円の贈与を繰り返す場合、5年間で2,500万円分を贈与税の負担なく子どもや孫に与えることができます。しかしその贈与分に相続税が発生しますので、完全に非課税で財産を取得できるわけではありません。
一方、ここに基礎控除を適用すれば年間500万円の贈与に対して特別控除の前に110万円の控除が可能となり、相続時の課税も390万円×5年分に抑えられます(あるいは残った特別控除の枠を使って贈与税の負担なくもっと財産を贈与することもできる)。
このような、複数年にわたり基礎控除を使って安く贈与する手法は暦年贈与でも利用できますが、相続時精算課税では特別控除も活用しつつ暦年贈与の節税方法も併せて実践できるというメリットがあるのです。
贈与時点の価格で相続税を計算できる
相続時精算課税制度の大きな特徴に、「贈与時の評価額が相続税計算時にも採用される」ということが挙げられます。
この性質は、特に不動産や株式など将来的な価値上昇が見込まれる資産の贈与に有効活用できます。
贈与時点で2,500万円の価値を持つ土地を贈与したとしましょう。10年後の相続時点時に土地の価値が5,000万円に上がっていたとしても、相続税の計算には贈与時の2,500万円を使うことができます。
つまりこの例においては、将来の値上がり分2,500万円分が実質的に非課税で贈与できたことになり、大きな節税効果が得られたことになります。もし今後資産価値が上昇する見込みが高いのであれば、相続時精算課税を選択するメリットが大きいといえるでしょう。
収益物件による相続財産の増加が抑制できる
賃貸用の不動産など収益性のある物件は、それを所有して運用を続けることで現金を増やし続ける可能性があります。その結果、将来の相続財産を増大させ、相続時の税負担が大きくなるかもしれません。
しかしその収益物件を贈与しておけば、当該物件から生じる利益も受贈者の所得となりますので、将来の相続財産の増加を抑制することができます。
不動産の贈与には大きな贈与税がかかるおそれもありますが、相続時精算課税制度を選択していればそのときの負担も大きく軽減できます。さらに、収益物件の運営がうまくいけば相続時点で納税資金に使える現金が入ってきていますので、納税資金対策も同時に実現されます。
選択前に確認すべきデメリット
相続時精算課税制度の選択が、必ずしも節税等のメリットをもたらすとは限りません。たとえば以下のようなデメリットが存在することについては理解しておくべきです。
・評価損に対しても相続税の負担が発生する
・小規模宅地等の特例が使えない
この2点について詳細を見ていきましょう。
評価損に対しても相続税の負担が発生する
上述のとおり、相続時精算課税には「贈与時の評価額が相続税の計算に採用される」という特徴があります。これはメリットをもたらすこともある反面で、場合によってはデメリットにもなり得る特徴でもあります。
贈与時の評価額が将来の相続税計算の基準となるため、資産価値が下落したとしても当初の相対的に高い評価額に基づいて課税されてしまうためです。
「相続時精算課税制度を利用せずに相続した方が結果的に税負担は安くなっていた」ということも起こり得るのです。
そのため節税効果も期待するのであれば、価値の変動が激しく評価が下がる可能性も十分にあるときは慎重な判断が求められます。
小規模宅地等の特例が使えない
「小規模宅地等の特例」が使えないという点も、土地を贈与する前に留意しておきたい大きな特徴です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用地などの評価額を大幅に減額(最大80%)できる制度で、土地の相続が発生するシーンではとても重要な役割を担う制度です。この特例を使えるかどうかで相続の負担が大きく変わることもあります。
しかし相続時精算課税制度を選択して土地を贈与していた場合、相続時にこの特例を適用して評価額を下げることはできません。贈与時点の価格を用いて相続税の計算を行う必要があります。
そこで「この土地は、相続で取得した場合に小規模宅地等の特例が使えそうだ」という場合には相続時精算課税制度を使って贈与すべきかどうか慎重に検討を進める必要があるでしょう。
----------------------------------------------------------------------
宮本税理士事務所
〒661-0025
兵庫県尼崎市立花町1-28-4 グレストハイツ102
電話番号 : 06-6421-3361
FAX番号 : 06-6421-3362
尼崎市で相続税申告を任せる
----------------------------------------------------------------------