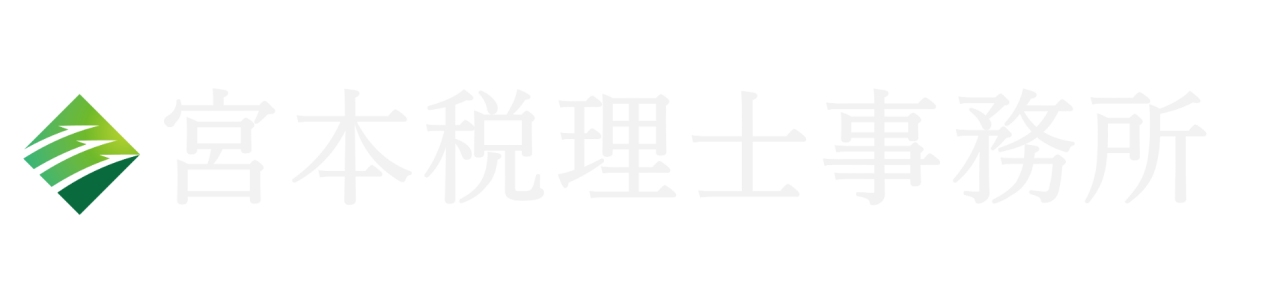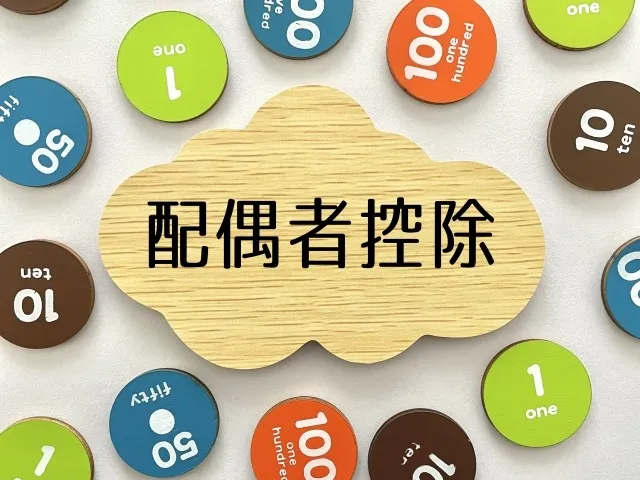相続税の配偶者控除が利用できる方・控除額・利用の手続きとは
2025/04/03
亡くなった方の夫や妻であれば、遺産を取得した際にかかる相続税の負担を大きく下げることができます。これは「配偶者控除」の恩恵であり、ほかの控除制度と比べても大きな税額軽減の効果が期待できるものです。
ただしこの制度を利用するには一定の要件を満たす必要があり、相続税の申告も欠かせません。そこで配偶者控除の利用を考える方に向けて、当記事では基本的な仕組みから利用の手続きまで、最低限知っておきたい配偶者控除のポイントをご紹介します。
配偶者控除が利用できる方の範囲
配偶者控除が利用できるのは「被相続人の配偶者」です。
亡くなった方の夫または妻として法的に認められている必要があり、これはつまり「事実上の配偶者では不十分」だという意味になります。法的に夫婦として認められるには婚姻の届出を行わなければなりませんので、この手続きを役所で行っていない内縁の夫・内縁の妻だとここでいう配偶者には該当しません。
他方、相続人であることは要件とされていません。
民法上、配偶者は常に相続人になると規定されていますので婚姻届を出して配偶者になっている方であれば相続に際して何ら手続きを行うことなく当然に相続人になりますが、相続放棄をした場合には相続人ではなくなります。
相続放棄をすると遺産を相続することはなくなりますので相続税についても考慮する必要がなくなるケースが多いですが、遺言書で「○○(妻)に不動産Xを遺贈する」旨の記載があると財産をもらい受けることができます。しかし配偶者であれば、相続人ではなくても、相続税が課税されるほどの遺贈がなされたとしても配偶者控除が使えるのです。
控除額の大きさ
配偶者控除の適用を受けると、配偶者が実際に取得した遺産の額がある金額に達するまでは相続税がかからなくなります。
この金額とは、少なくとも「課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額」を指します。そのため1億円でも10億円でも、それが法定相続分に従って按分した金額なのであれば、配偶者に相続税の負担は発生しません。
そして、仮に法定相続分相当額を超えて取得したとしても、その額が「1億6,000万円」まであれば同様に非課税となります。
言い換えると、「法定相続分を超える割合を取得し、かつ1億6,000万円超の財産を取得した」というケースに該当しなければ夫や妻に相続税の負担は発生しないと説明できます。
例1)相続人は妻と長男(法定相続分は1/2ずつ)、遺産は1億円。
・・・妻が全財産を取得しても非課税にできる。
例2)相続人は夫と長男・長女(法定相続分は夫に1/2、長男と長女は1/4ずつ)、遺産は5億円。
・・・夫は法定相続分2億5,000万円を取得しても非課税にできる。
・・・法定相続分を超え3億円を取得したときは5,000万円分に対して相続税が課税される。
例3)相続人は妻と父・母(法定相続分は妻に2/3、父と母は1/6ずつ)、遺産は1億8,000万円。
・・・妻は法定相続分1億2,000万円を取得しても非課税にできる。
・・・法定相続分を超え1億6,000万円を取得しても非課税にできる。
・・・1億6,000万円を超えるとその部分に対して相続税が課税される。
控除を利用するための手続き
配偶者控除の適用を受けるには、まず配偶者が取得する財産を確定させないといけません。そこで相続人が複数いるなら遺産分割協議を済ませておく必要があります。
そのうえで、相続税の申告も欠かせません。遺産の総額が基礎控除額より小さいなどの理由で納付額が発生しないときは申告をしなくても問題ありませんが、配偶者控除を利用するなら納付額が0円でも申告をしないといけません。
遺産分割協議を済ませておく
控除額は、配偶者が実際に取得した財産の大きさを基に算出します。反対に、相続税の申告期限(おおよそ相続開始から10ヶ月間)までに分割がされていない財産については控除の対象にはできません。
※遺言書に従い遺産を取得するのでも問題ない。また、協議によらず家庭裁判所の調停もしくは審判による分割でも問題ない。しかしいったん遺産分割が成立し、財産が分配された後で遺産分割をやり直した場合には適用できない。
ただ、相続人らで分割の仕方で揉めているなど、何らかの事情によって申告期限に遺産分割が間に合わないケースもあります。そんなときはいったん法定相続分で相続税の申告を行い、そこに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。
この手続きを行うことで、申告期限を過ぎても3年以内であれば遺産分割を行いその取得分に対して配偶者控除を適用させることが可能となります。
※申告期限から3年経っても分割ができないやむを得ない事情があるときでも、税務署長の承認を受ければ配偶者控除の適用を受けられる。ただしそのやむを得ない事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割を済ませないといけない。
納付額が0円でも申告を行う
遺産の総額が[3,000万円+600万円×法定相続人の数]で算出される基礎控除額以下であるなら、配偶者控除を使うまでもなく非課税となり、納付すべき額は0円となります。この場合は相続税の申告も不要です。
一方、配偶者控除を適用した結果納付すべき額が0円になるときでも相続税の申告は必要です。申告作業自体が当該控除の適用条件とされているためです。
そこで配偶者控除を利用するときは、取得した財産の種別に応じて作成する第9表~第15表、課税価格の合計額や相続税の総額を計算する第1表・第2表など基本的な申告書を用意するとともに第5表にあたる「配偶者の税額軽減額の計算書」も作成しましょう。
こちらから各種申告書の様式および記載例が確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06pdf/C18.pdf
また、申告時には次の書類を添付します。
戸籍の謄本など相続人であることを証明する書類
遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写しなど取得した財産を証明する書類
(遺産分割協議書の写しを添付する場合)遺産分割協議書に押印した印鑑に係る相続人全員分の印鑑登録証明書
なお、申告書にあえて記載しないなどの理由によって「仮装・隠蔽されている財産がある」と評価された部分があると、その財産については控除の対象から外れるため注意してください。また、相続税の計算や申告書の作成、その前提として必要な財産評価にも高い専門性が求められるため、申告や控除の適用でミスが起こらないよう税理士に相談することをおすすめします。
----------------------------------------------------------------------
宮本税理士事務所
〒661-0025
兵庫県尼崎市立花町1-28-4 グレストハイツ102
電話番号 : 06-6421-3361
FAX番号 : 06-6421-3362
尼崎市で相続対策について相談
----------------------------------------------------------------------